憤妵
敄枌嵽椏僨僶僀僗尋媶夛偺戞係夞尋媶廤夛偑丄乽柧擔偺揹巕僨僶僀僗傪巟偊傞 敄枌怴嵽椏乿偲偄偆僥乕儅偺壓偵丄2007 擭11 寧2丄3 擔偺2 擔娫丄嫗搒巗撪偺 棿扟戝妛戝媨妛幧惔榓娰偵偰奐嵜偝傟偨丅夁嫀嵟崅偺184 柤偺嶲壛幰偲60 審偺 榑暥搳峞傪廤傔丄僠儏乕僩儕傾儖丄岥摢敪昞丄億僗僞乕敪昞丄儔儞僾僙僢僔儑 儞丄嬈幰揥帵偲惙戝偵峴傢傟偨丅崱擭傕嶻嬈媄弍憤崌尋媶強師悽戙敿摫懱尋媶 僙儞僞乕偺淎悾慡岶愭惗傪偼偠傔偲偡傞奺奅偺挊柤側愭惗曽傪懡悢彽懸偟丄傾 儌儖僼傽僗敿摫懱偺楌巎偐傜嵟愭抂媄弍偵帄傞傑偱婱廳側島墘傪偄偨偩偒丄戝 曄廩幚偟偨撪梕偲側偭偨丅IV 懓宯敿摫懱丄巁壔暔敿摫懱丄桳婡暔敿摫懱丄桿揹 懱丄怴嵽椏側偳丄擔崰偼婄傪崌傢偣傞偙偲偺側偄堎暘栰偺尋媶幰丒媄弍幰偑堦 摪偵夛偟偰帺桼偵媍榑偡傞偙偲偱丄怴偟偄敪尒傗媄弍偺梈崌側偳丄怴慛妿偮幙 偺崅偄忣曬岎姺偺応傪採嫙偱偒偨偲峫偊偰偄傞丅嶲壛幰偺傾儞働乕僩寢壥偱 偼丄乭枮懌偟偨乭丄乭懕偗偰梸偟偄乭偲偄偆惡傪懡悢偄偨偩偄偨丅
嶲壛幰慡堳偺搳昜偵傛偭偰寛掕偝傟傞傾儚乕僪偼崱夞偐傜俁柤偵憹榞偝傟丄 棿扟戝妛偺妢愳抦梞偝傫丄崙棫戜榩壢媄戝妛偺梩暥徆偝傫丄嬨廈戝妛偺埌曯抭 峴偝傫偵庼梌偝傟偨丅
杮尋媶夛偺奐嵜偵偁偨傝彆惉偄偨偩偄偨丄嵿抍朄恖 拞晹揹椡婎慴媄弍尋媶強丄 嵿抍朄恖 娭惣僄僱儖僊乕丒儕僒僀僋儖壢妛尋媶怳嫽嵿抍偵怺偔姶幱偡傞丅
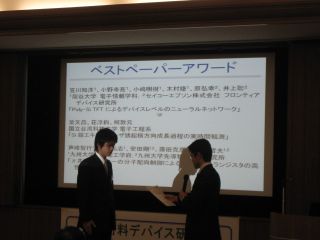
僠儏乕僩儕傾儖
乽柧擔偺揹巕僨僶僀僗傪巟偊傞嵽椏乿偺戙昞偲偟偰巁壔暔敿摫懱丒桳婡暔敿 摫懱偵偮偄偰丄婎慴偐傜偦偺摿挿丄墳梡偵偮偄偰丄弶妛幰偵傕廩暘棟夝偱偒傞 撪梕偱島墘傪偄偨偩偄偨丅崅抦岺壢戝妛偺屆揷愭惗偵偼丄巁壔暔TFT 傊偺墳梡 偵偮偄偰巁壔暔敿摫懱偺嵽椏桪埵惈偲幚梡壔傊偺壽戣偵偮偄偰丄傑偨戝嶃晎棫 戝妛偺撪摗愭惗偵偼丄桳婡暔敿摫懱偺岝d巕暔惈偵偮偄偰島墘傪偄偨偩偄偨丅 嵟嬤偺崙撪奜偺尋媶寢壥偲偲傕偵偛帺恎偺尋媶寢壥傕徯夘偟偰偄偨偩偒奺50 暘 偺島墘偼丄旕忢偵廩幚偟偨撪梕偱偁偭偨丅島墘廔椆屻傕妶敪側媍榑偑岎傢偝傟丄 椉暘栰偺姶怱偺崅偝傪偆偐偑傢偣偨丅
僆乕儔儖僙僢僔儑儞
僙僢僔儑儞Ia乽桳婡嵽椏丒僨僶僀僗乿偱偼3 審偺敪昞偑側偝傟偨丅傑偢丄嬨 廈戝妛偺埨払巵偑乽桳婡敪岝惈敄枌僨僶僀僗偺怴揥奐乿偲戣偡傞彽懸島墘傪峴 偭偨丅桳婡摿桳偺帺桼搙偺崅偄嵽椏愝寁偵傛偭偰丄條乆側敪岝攇挿偺桿摫曻弌 偑壜擻偱偁傞偙偲丄傑偨丄桳婡敿摫懱嵽椏偱偁偭偰傕揔愗側揹嬌偲曻擬愝寁偵 傛偭偰悢MA/cm2 偲偄偆嬌傔偰崅偄揹棳枾搙傪払惉偱偒傞偙偲側偳丄桳婡敪岝僨 僶僀僗傗偦偺媶嬌偺巔偱偁傞儗乕僓乕偺壜擻惈偑嬶懱揑偵尒偊傞傛偆側撪梕偱 偁偭偨丅僙僀僐乕僄僾僜儞偺惵栘巵傛傝丄桳婡僩儔儞僕僗僞偵偍偗傞摿惈偺 敿摫懱枌岤埶懚惈偵偮偄偰敪昞偑偁偭偨丅僎乕僩愨墢枌偲偺奅柺偩偗偱側偔丄 斀懳懁偺奅柺偵偍偗傞奅柺弨埵偑幚嵺偵鑷揹埑偵戝偒偔塭嬁偟偰偄傞偙偲傪掕 検揑偵帵偟偨丅愮梩戝妛偺徏尨巵傛傝丄桳婡懡寢徎敄枌偵偍偗傞揹奅岠壥堏 摦搙偺寢徎僪儊僀儞僒僀僘埶懚惈偲壏搙埶懚惈偵偮偄偰曬崘偑偁偭偨丅撈帺偺 巐扵恓傪傕偪偄傞堏摦搙昡壙憰抲傪梡偄丄儌僨儖偲偺斾妑偐傜僪儊僀儞嫬奅偺 僶儕傾崅偝傗儂乕儖偺桳岠幙検傪媍榑偟偨丅
僙僢僔儑儞Ib乽巁壔暔嵽椏丒僨僶僀僗乿偱偼3 審偺敪昞偑側偝傟偨丅杒棨愭 抂戝妛堾戝妛偺杧揷巵偼丄FET 宆嫮桿揹懱儊儌儕偺摿惈岦忋偵偮偄偰敪昞偟偨丅 拞娫揹嬌傪梡偄偨嫮桿揹懱儊儌儕偱偼楢懕揑側撉傒弌偟偵栤戣偑偁偭偨偲偙傠 傪丄撉傒弌偟僷儖僗側偳傪岺晇偡傞偙偲偵傛傝夝徚偟丄撉傒弌偟懴惈108 夞埲忋丄 150亷偱偺曐帩帪娫偑10 擭埲忋摼傜傟傞偙偲傪帵偟偨丅JST 偺暯徏巵偼丄儚僀僪 僊儍僢僾p 宆敿摫懱偱偁傞LaCuOSe 傊偺惓岴僪乕僺儞僌偲桳婡LED 梡偺揹嬌墳 梡偵偮偄偰敪昞偟偨丅廬棃傛傞1 寘崅偄1021 cm-3 偺崅擹搙僪乕僺儞僌傪払惉偟丄 桳婡LED 梡偺惓岴桝憲憌偱偁傞NPB 傊偺惓岴拲擖忈暻偑廬棃巊傢傟偰偄傞ITO 傛傝傕掅偔梷偊傞偙偲偑偱偒傞偙偲傪帵偟偨丅搶杒戝妛偺愳嶈巵偐傜偼丄彽懸 島墘偲偟偰乽巁壔暔僄儗僋僩儘僯僋僗乿偵偮偄偰嬌傔偰峀斖側徯夘偑側偝傟偨丅 巁壔暔挻揱摫嵽椏偵抂傪敪偡傞摨巵偺壺乆偟偄尋媶惉壥偺悢乆偵偮偄偰丄惛枾 僄僺僞僉僔儍儖媄弍傗寚娮傪揙掙揑偵捛偄崬傫偩忋偱惛枾偵僪乕僺儞僌偡傞媄 弍丄僐儞價僫僩儕傾儖庤朄偺廳梫惈側偳丄巁壔暔埲奜偺尋媶幰偵偲偭偰傕帵嵈 偵晉傓島墘偱偁偭偨丅
僙僢僔儑儞IIa 偍傛傃IIb乽嘩懓宯僾儘僙僗丒僨僶僀僗乿偱偼丄崱擭傕偨偔偝 傫偺嫽枴怺偄敪昞偑偁偭偨丅崱夞偺摿挜偼丄敄枌僩儔儞僕僗僞偽偐傝偱側偔丄 MOSLSI 偵娭偡傞敪昞傕懡偔偁傝丄暆峀偄暘栰偐傜搳峞偑廤傑偭偨偙偲偱偁傞丅 傑偨丄戜榩偐傜偺搳峞傕偁傝丄崙嵺怓朙偐側僙僢僔儑儞偲側偭偨丅彽懸島墘幰 偺嬨廈戝妛偺媨旜巵偐傜丄乽僔儕僐儞宯傊僥儘挻峔憿媄弍偺憂弌偲枹棃宆僨僶僀 僗偺柌乿偲偄偆僥乕儅偱丄婇嬈帪戙偐傜戝妛偵偍偗傞尋媶偺偁傝偐偨偵偮偄偰 偺島墘偑偁偭偨丅摨巵偑丄嬯擸偺拞偱丄偳偺傛偆側巚偄偱丄尋媶偺柌傪娧偄偨 偐偲偄偆懠偱偼暦偗側偄報徾揑側島墘偱偁偭偨丅僴僀僥僢僋僔僗僥儉偺嵅栰巵 偐傜偼丄愒奜慄儗乕僓傪巊偭偨晄弮暔傾僯乕儖媄弍偵娭偡傞敪昞偑偁偭偨丅DLC 枌傪岝媧廂憌偲偟偰梡偄偰丄楢懕攇愒奜慄儗乕僓偵傛傞僀僆儞拲擖晄弮暔偺妶 惈壔傪専摙偟偨丅B 傗P 偵懳偡傞妶惈壔棪偑傎傏100亾偲偄偆崅偄岠棪傪幚徹偟 偨丅嬨廈戝妛偺捗懞巵偐傜偼丄Al 桿婲憌岎姺惉挿朄偵傛傞懡寢徎SiGe 偺掅壏宍 惉偺採埬偑偝傟偨丅Ge 擹搙傪曄壔偝偣偨偝傑偞傑側SiGe 枌傪梡偄偰丄偦偺寢徎 壔忬懺傪娤應偟偨偲偙傠丄慡Ge 擹搙偵偍偄偰乮111乯偵桪愭攝岦偟偨SiGe 寢徎 偺惉挿傪妋擣偱偒偨丅崙棫戜榩壢媄戝偺梩巵偐傜偼丄Si 敄枌偺僄僉僔儅儗乕僓 桿婲墶曽岦寢徎惉挿夁掱偺幚帪娫娤應朄偺採埬偑偁偭偨丅偙偺庤朄傪梡偄傞偙 偲偱丄墶曽岦惉挿懍搙偼夁椻媝搙偵娭傢傜偢堦掕偱偁傞偙偲偑妋擣偱偒偨丅嫗 搒戝妛偺婽堜巵偐傜偼丄僾儔僘儅偑嵟愭抂MOSLSI 偵媦傏偡僟儊乕僕偵偮偄偰偺 嫽枴怺偄敪昞偑偁偭偨丅僎乕僩愨墢枌偩偗偱側偔丄愙崌攋夡偵傕戝偒側僟儊乕 僕傪桿婲偡傞壜擻惈傪帵嵈偟偨丅柧帯戝妛偺椦揷巵偐傜偼丄僗僷僢僞朄傪梡偄 偨TiN 僎乕僩嬥懏傪桳偡傞MOSFET 偺揹婥摿惈偵娭偡傞敪昞偑偁偭偨丅僗僷僢僞 帪偺拏慺棳検偺曄壔偑僩儔儞僕僗僞偺偟偒偄抣傗倗倣偵梌偊傞塭嬁傪夝愅偟丄 嵟揔忦審傪柧傜偐偵偟偨丅
僙僢僔儑儞IIc乽愨墢枌丄夞楬乿偱偼3 審偺敪昞偑側偝傟偨丅僙僀僐乕僄僾僜 儞偺揷拞巵偼塼懱悈慺壔億儕僔儔儞傪慜嬱懱偲偟偰梡偄偨SiO2 愨墢枌宍惉傪曬 崘偟偨丅億儕僔儔儞偺巁壔斀墳傪惂屼偡傞偨傔偵丄億儕僔儔儞揾晍屻丄拏慺拞 偲戝婥摍巁慺暘埑壓偱偺懡抜奒從惉傪岺晇偟偰椙幙偺SiO2 枌宍惉忦審傪尒弌偟 偨丅桿揹棪丄奅柺弨埵枾搙丄儕乕僋揹棳摿惈偐傜丄摨嵽椏偺TFT 僎乕僩愨墢枌 偲偟偰偺揔梡壜擻惈傪帵偟偨丅杒棨愭抂戝妛堾戝妛偺Hana 巵偼僔儕僐儞枌偺寢 徎壔傪桿婲偡傞僔乕僪憌偲偟偰梡偄傞YSZ 枌偺嵟揔宍惉忦審傪媍榑偟偨丅僗僷 僢僞惉枌慜偺僞乕僎僢僩偺巁壔僾儘僙僗偑YSZ 枌宍惉偵廳梫偱偁傞偙偲傪採帵 偟偨丅偦偟偰丄嫮偄乮侾侾侾乯攝岦傪帵偡YSZ 偺宍惉偺偨傔偺嵟揔僞乕僎僢僩 巁壔忦審傪帵偟偨丅搶嫗岺寍戝妛偺扥屶巵偼丄僠儍僱儖椉懁偵LDD 峔憿傪傕偮n 宆TFT 偺儂僢僩僉儍儕儎敪惗偵偮偄偰丄僔儈儏儗乕僔儑儞傪梡偄偨媍榑傪峴側 偭偨丅LDD-n-椞堟偺僪乕僺儞僌擹搙偑掅偔丄妿偮僎乕僩媦傃僪儗僀儞揹埑偑戝偒 偄偲偒偵偼丄椉LDD 椞堟偵偍偄偰摨帪偵尠挊側揹埵崀壓偑敪惗偟丄僜乕僗懁偵 偍偄偰傕儂僢僩僉儍儕儎楎壔偑惗偠傞壜擻惈傪曬崘偟偨丅


億僗僞乕僙僢僔儑儞
億僗僞乕僙僢僔儑儞偼丄岥摢敪昞偝傟偨榑暥傪娷傔偰56 審偺敪昞傪尋媶廤夛 弶擔偺16:00-18:00 偲2 擔栚偺13:20-15:20 偺俀夞偵暘偗偰峴偭偨丅崱夞偼丄 億僗僞乕敪昞捈慜偵岥摢敪昞幰傪彍偔曽偵丄1 審偁偨傝1.5 暘丄奺夞偺慡懱偺帪 娫偲偟偰30 暘掱搙偺僔儑乕僩僾儗僛儞僥僀僔儑儞傪偍婅偄偟偨丅傎偲傫偳偺敪 昞幰偼丄惂尷帪娫撪偵撪梕偺梫揰傪揑妋偵弎傋傜傟丄慡懱揑偵峇偰偨姶偠偼柍 偔丄斾妑揑僗儉乕僗偵恑峴偟偨偲巚偊傞丅奺敪昞帪娫偼抁偐偭偨偑丄捈屻偵峴 偆億僗僞乕敪昞傊偺婱廳側忣曬尮偲偟偰偺婡擻偼丄廫暘偵壥偨偟偨偲姶偠傜傟 偨丅億僗僞乕敪昞帺懱偼丄惔榓娰侾丄2 奒偺2 僼儘傾慡懱傪梡偄偰峴傢傟丄 偦偺廫暘側峀偝偲僔儑乕僩僾儗僛儞僥僀僔儑儞偱偺娙扨側撪梕攃埇傕偁偭偰偐丄 奺億僗僞乕慜偱偼擬婥偵偁傆傟偨摙榑偑側偝傟丄僙僢僔儑儞廔椆屻傕帪娫傪朰 傟偨偐偺傛偆偵媍榑偑懕偄偨丅傑偨丄岥摢敪昞偱暦偄偨榖傪傛傝峀偔丄怺偔媍 榑偱偒傞応偲偟偰傕桳岠偵摥偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅
儔儞僾僙僢僔儑儞
杮尋媶廤夛偱偼丄僶儞働僢僩偲摨帪恑峴偱偄偔偮偐偺僩僺僢僋僗島墘傪暦偔 儔儞僾僙僢僔儑儞偑堦偮偺栚嬍偲側偭偰偄傞丅嶐擭偼丄搶奀戝妛偺媏抮惤愭惗 偵丄乽昞柺暔棟偑惗傓亀怗敪亁乣楌巎偺拞偺嫵孭乣乿偺戣栚偱丄擔杮偺敿摫懱尋 媶偺阾柧婜偐傜巒傑傞楌巎偵偮偄偰丄尋媶偑偝傑偞傑側嬊柺傪孞傝曉偟側偑傜 恑揥偟偔偙偲丄乭夦偟偄棟夝乭傪惓柺偐傜峌傔捈偡偙偲偺廳梫惈側偳丄偙傟偐傜 傪扴偆尋媶幰偵偲偭偰椙偒嫵孭偲側傞撪梕傪娷傫偩偛島墘傪偟偰偄偨偩偄偨丅 崱擭傕偙偺棳傟傪宲彸偟偮偮丄杮尋媶廤夛偺僥乕儅乽柧擔偺揹巕僨僶僀僗傪巟 偊傞敄枌怴嵽椏乿偵娭楢偟偰丄嶻憤尋 師悽戙敿摫懱尋媶僙儞僞乕挿偺淎悾慡岶 愭惗偵偛島墘偟偰偄偨偩偄偨丅戣栚偼乽敄枌怴嵽椏偲僨僶僀僗暔棟偑愗傝奐偔 僒僀僄儞僗丒僀僲儀乕僔儑儞乿偱丄1975 擭偵弶傔偰偺pn 惂屼偑曬崘偝傟偨摉帪 妚怴揑側怴嵽椏偱偁偭偨悈慺壔傾儌儖僼傽僗僔儕僐儞偐傜丄尰嵼偺Si MOS 僾儘 僙僗偱尋媶偑恑傔傜傟偰偄傞high-K 嵽椏偵帄傞傑偱丄怴嵽椏尋媶偺妝偟偝丄嫽 暠丄偦偟偰崲擄偑揱傢偭偰偔傞偍榖偱偁偭偨丅乽怴嵽椏偵偐偐傢傞尋媶僌儖乕僾 傪偄偐偵摦偐偡偐乿偐傜巒傑傝抦揑嵿嶻尃側偳偵帄傞懡偔偺幙栤偵懳偟偰丄偦 傟傜傊偺夞摎偩偗偱側偔丄嶐崱偺戝妛偺巔惃傊偺桱偄丒婜懸傗暷崙偵偍偗傞戝 妛偺尋媶J敪偺帠忣傪娷傔丄徻偟偔挌擩偵偍摎偊偄偨偩偄偨偙偲偑報徾偵巆傞丅
偦偺屻丄搳峞榑暥偐傜摿偵僩僺僢僋僗惈偺崅偄3 審偺島墘傪偍婅偄偟偨丅棿 扟戝妛偺妢愳巵偐傜偼乽Poly-Si TFT 偵傛傞僨僶僀僗儗儀儖僲僯儏乕儔儖僱僢僩 儚乕僋乿偲戣偟丄掅壏億儕僔儕僐儞傪怴偟偄揹巕夞楬傊墳梡偡傞愭恑揑側尋媶 偵偮偄偰曬崘偑偁偭偨丅僉儍僲儞偺塤尒巵偐傜偼丄乽傾儌儖僼傽僗巁壔暔敿摫 懱:In-Ga-Zn-O TFT 偲偦偺夞楬乿偲戣偟丄怴偟偄敿摫懱嵽椏偱偁傞傾儌儖僼傽僗 巁壔暔敿摫懱TFT 偺摿挜傪傢偐傝傗偡偔愢柧偟偰偄偨偩偔偲偲傕偵丄尰嵼傑偱 偵暋悢幮偱揹巕儁乕僷乕丄桳婡EL 僥儗價偺帋嶌昳敪昞偑偝傟偰偄傞偙偲側偳偺 曬崘偑側偝傟偨丅嵟屻偵丄愮梩戝妛偺搉绯巵偐傜丄乽僼儗僉僔僽儖僨僶僀僗偵岦 偗偨廲宆桳婡僩儔儞僕僗僞乿偲戣偟丄桳婡SIT 僩儔儞僕僗僞偺尰忬偲壽戣傗桳 婡敪岝僩儔儞僕僗僞傊偺墳梡側偳偵偮偄偰偺曬崘偑偁偭偨丅幙栤帪娫偑廫暘偲 偼偄偊側偄忬嫷偱偼偁偭偨偑丄嫽枴怺偄島墘偲妶敪側幙媈偑側偝傟偨偙偲丄怺 栭傑偱偍晅偒崌偄偄偨偩偄偨島巘偺愭惗曽偲嶲壛幰偺奆條偵夵傔偰屼楃怽偟忋 偘傞丅
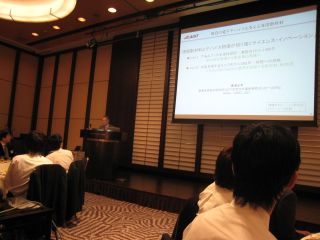

揥帵丒峀崘
敄枌嵽椏僨僶僀僗尋媶夛偺尋媶廤夛偱偼丄尋媶奐敪婡娭偲娭楢婇嬈偲偺僐儈 儏僯働乕僔儑儞傪恾傞栚揑偱丄偙傟傑偱傕丄尋媶廤夛夛応偵偍偗傞婇嬈揥帵丒 傾僽僗僩儔僋僩廤傊偺峀崘宖嵹傪峴偭偰偒偨丅
揥帵夛応偼丄億僗僞乕夛応偲暪愝偟偰偍傝丄壛偊偰僐乕僸乕僒乕價僗傕偁偭 偰丄懡偔偺嶲壛幰偑懌傪塣傫偩丅億僗僞乕僙僢僔儑儞傗拫媥帪娫偵丄桳堄媊側 妶摦偑偱偒偨偲暦偄偰偄傞丅揥帵婇嬈偺曽乆偵偼丄幚婡偺揥帵側偳傕偟偰偄偨 偩偒丄偨偄傊傫桳堄媊側忣曬廂廤偺応偲側偭偨偲巚傢傟傞丅傑偨丄揥帵僐儅乕 僔儍儖偲偟偰丄媥宔帪娫偵丄揥帵撪梕偺奣梫丒婇嬈偺嬈柋斖埻側偳傪徯夘偄偨 偩偄偨偑丄媥宔帪娫偵傕偐偐傢傜偢丄懡悢偺嶲壛幰偵帹傪孹偗偰偄偨偩偒丄岲 昡偱偁偭偨丅峀崘偲偟偰偼丄傾僽僗僩儔僋僩廤偺昞巻丒棤昞巻側偳偵丄忋幙巻 偵傛傞峀崘傪宖嵹偝偣偰偄偨偩偄偨丅嶲壛幰180 柤傪偼偠傔偲偡傞200 晹埲忋 偑棳晍偟丄傑偨丄庤慜枴慩偱偼偁傞偑丄廩幚偟偨撪梕偺傾僽僗僩儔僋僩廤偼丄 崱屻傕悢擭乣廫悢擭偼丄嶲壛幰偺傒側偝傑側偳偵嶲徠偝傟傞偱偁傠偆偐傜丄峀 崘岠壥偼愨戝偩偲婜懸偡傞丅
埲壓偼丄揥帵丒峀崘偄偨偩偄偨婇嬈偺儕僗僩偱偁傞丅嵟屻偵側傞偑丄弌揥婇 嬈偺傒側偝傑丄懌傪塣傫偱偄偨偩偄偨嶲壛幰偺傒側偝傑偵丄怱傛傝姶幱傪怽偟 忋偘偨偄丅
揥帵
- 僒儞儐乕揹巕 姅幃夛幮
- 傾僕儗儞僩丒僥僋僲儘僕乕 姅幃夛幮
- 僴僀僜儖 姅幃夛幮
- 姅幃夛幮 儕僈僋
- 姅幃夛幮 僄僀僄儖僄僗僥僋僲儘僕乕
- 桳尷夛幮 僨僓僀儞僔僗僥儉
- 姅幃夛幮 僔儖僶僐丒僕儍僷儞
- 姅幃夛幮 僄僺僥僢僋
- 姅幃夛幮 僀儞僞乕僫僔儑僫儖丒僒乕儃丒僨乕僞乕
峀崘
- 僒儞儐乕揹巕 姅幃夛幮
- 廧桭廳婡夿傾僪僶儞僗僩儅僔僫儕乕 姅幃夛幮
- 姅幃夛幮 僄僀僄儖僄僗僥僋僲儘僕乕
- 姅幃夛幮 擔杮惢峾強
- 姅幃夛幮 傾儖僶僢僋